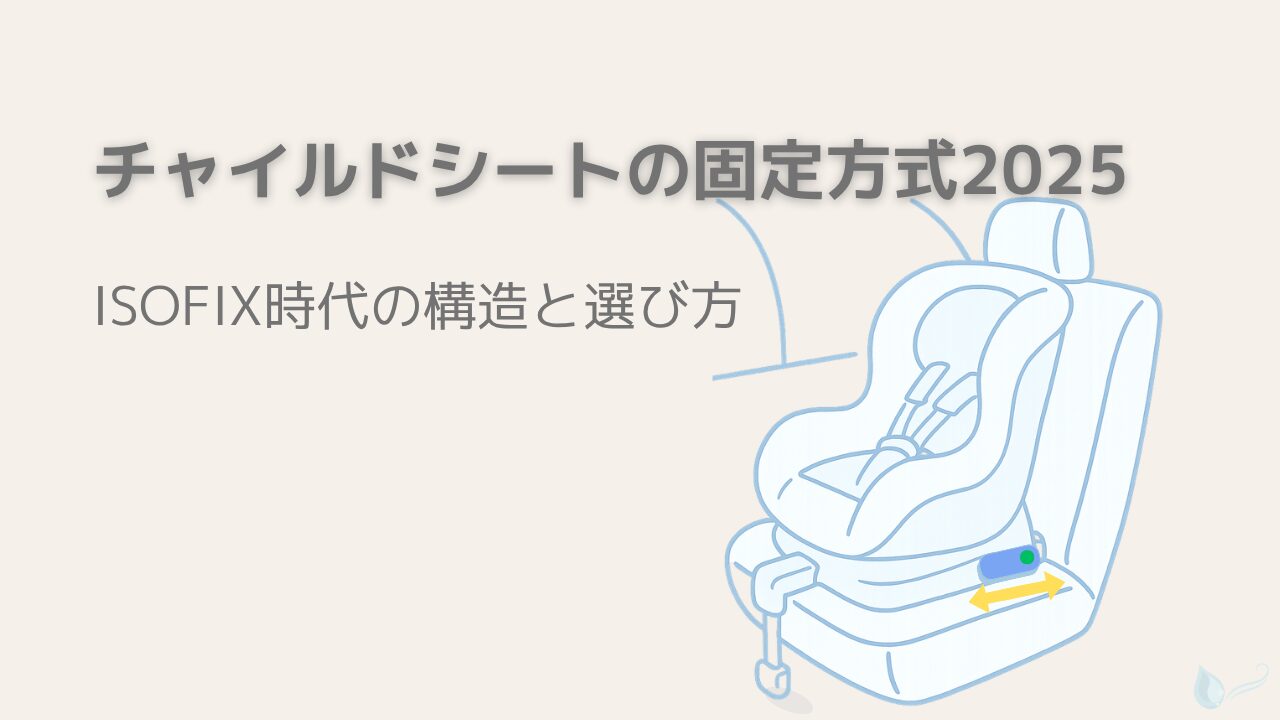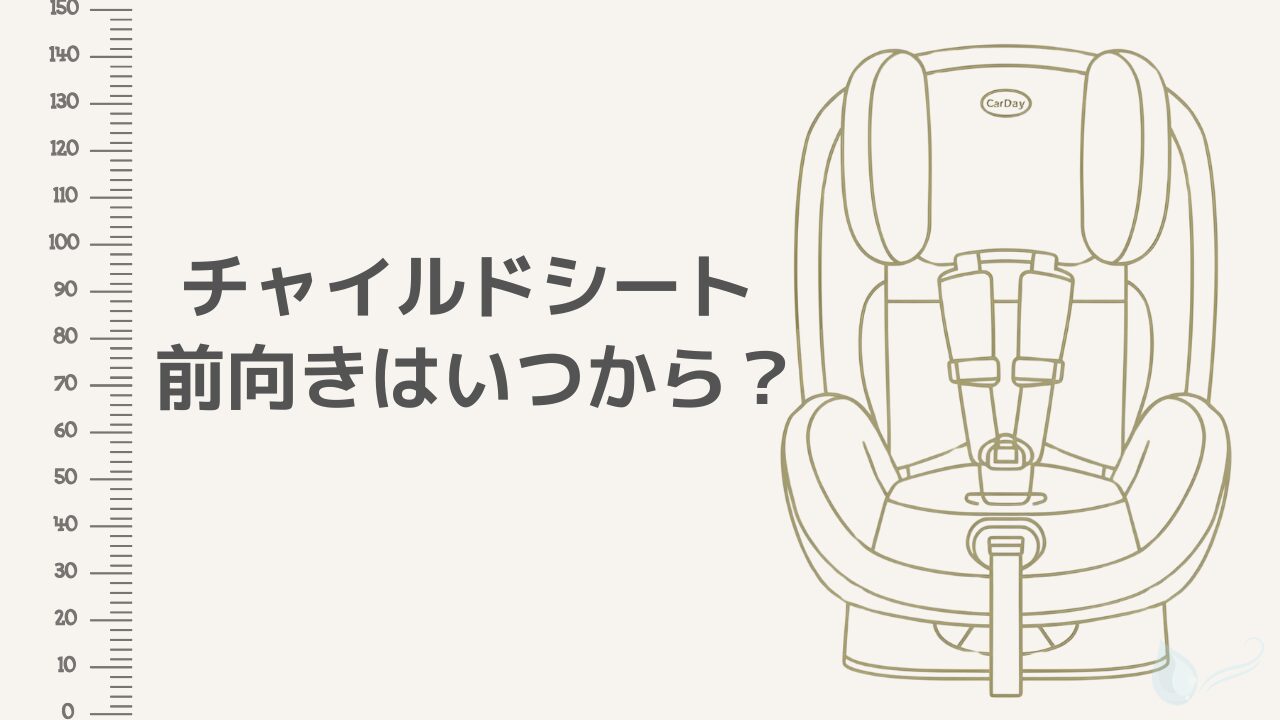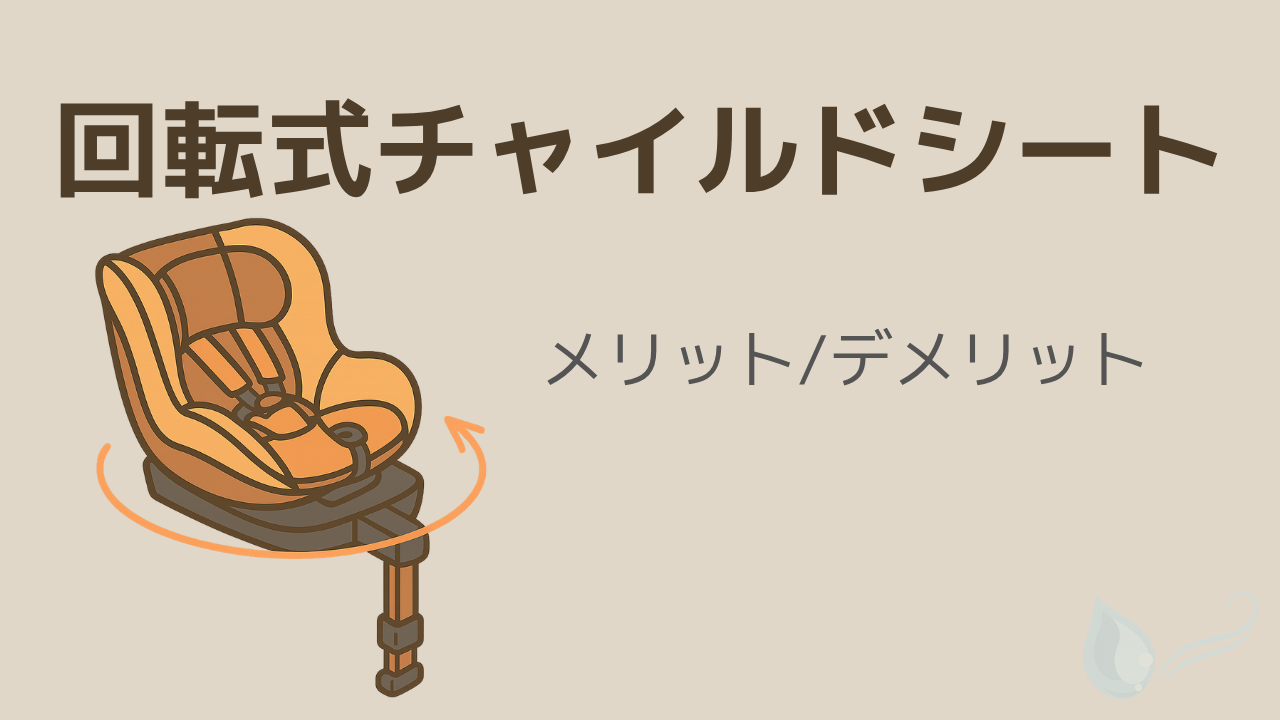泣いても安全。チャイルドシートを嫌がらなかった、わが家の小さなルール

はじめに
昔、海外の推理小説の中で、こんな一文を読んだことがあります。
――「子どもには、一度でもシートベルトをしない記憶を残してはいけない。」
正確な言葉までは覚えていませんが、その意味だけは今も印象深く残っています。
そして実際に子どもが生まれたとき、私はその言葉を思い出し、
“車に乗る=チャイルドシートに座る”という習慣を、最初から徹底しました。
その結果、わが家ではチャイルドシートを嫌がることが一度もありませんでした。
ぐずる場面さえほぼなく、自然と「乗るのが当たり前」になっていったのです。この記事では、この経験をきっかけに、
なぜ子どもがチャイルドシートを嫌がるのか、そしてどんな工夫で防げるのかを、
販売員として、そして一人の親として整理していきます。
チャイルドシートの種類や成長に合わせた選び方については、こちらの記事(チャイルドシートとジュニアシートの違い)でも詳しく解説しています。
💭 親として感じる“いちばんの難しさ”
泣いている子をそのままチャイルドシートに乗せるのは、正直つらいことです。
親も子どもも気持ちが落ち着かなくて、「今日は抱っこでいいか」と思いたくなる瞬間もある。
でも、泣いても子どもは死なない。
けれど、事故は――一瞬で取り返しがつかなくなる。
そのときに「たった一度だけ」「あのときだけ」と思っていた選択が、
一生の後悔に変わる可能性があるのが現実です。だからこそ、私は“泣いてもチャイルドシート”を譲らなかった。
どんなに短い距離でも、どんなに急いでいても、例外を作らなかった。
その積み重ねが「泣かない子」に育った一番の理由だと思います
「一度も“無しで乗らない”」が最大の対策
チャイルドシートを嫌がらないために、いちばん効果的なのは、
「車に乗る=チャイルドシートに座る」という習慣を最初の一回目から徹底することです。人間は、快・不快よりも“習慣”に強く影響されます。
とくに赤ちゃんは「これがいつもの流れ」と感じたことを疑わない。
だから、最初の数回で“当たり前”のパターンを作ってしまえば、
その後も自然と受け入れやすくなります。
🚫 “例外”が記憶になる
親として、泣いている子どもをそのまま乗せるのは本当に心が痛みます。
でも、一度だけ抱っこで乗せたという例外ができると、
子どもはそれを「泣けば抱っこしてもらえる」と記憶します。その一度が、何度も繰り返されるきっかけになる。
安全よりも“抱っこのぬくもり”を選びたくなるのは当然ですが、
そこをどう乗り切るかで、その後の習慣が決まります。
💡 わが家のルール
わが家では、「どんなに短距離でも、どんなに急いでいても、チャイルドシートは必ず」がルールでした。
体調が悪い日や機嫌が悪い日もありましたが、
“乗らない選択肢”を一度も作らなかったことが、いちばんのポイントだったと思います。
もちろん、泣かせたいわけじゃない。
でも、「泣いても安全な場所にいようね」と伝えることが、
最終的にいちばんの“安心”につながります。
チャイルドシートを安全に使うためには、正しく取り付けられているかを確認することも欠かせません。こちらの記事(ISOFIXでも油断禁物!取り付けミスあるあると正しい確認方法)で、よくある取り付けミスと対策を紹介しています。
👥 周囲とも共有を
祖父母や他の送迎をする人とも、ルールの共有が欠かせません。
「短い距離だからいいよね」
「抱っこで出るだけだから」
――その“ちょっとだけ”を防ぐためには、家族全員の共通認識が必要です。販売員としても、実際にそうした例を多く見てきました。
“一度も無しで乗らない”は、単なるマイルールではなく、家族の命を守る基本方針です。
もし嫌がるようになったら
どんなに気をつけていても、成長の過程で“イヤイヤ期”が訪れたり、
一時的にチャイルドシートを嫌がるようになる子はいます。
そんなときは、「泣かないようにする」よりも、“安心できる時間に戻す”ことを意識します。
🪞 まずは「焦らない」
泣かれると、親のほうも動揺してしまうもの。
でも、焦るとその空気が伝わって、子どももますます不安になります。
「よし、今日も安全ドライブだね」
「ベルト、カチンってしようか」そうやって落ち着いた声で、いつもと同じ声かけをするだけでも効果的。
“焦らない親”は、子どもにとって“安心の合図”になります。
🏠 家の中で練習してみる
車に乗せる前に、動かさない状態で慣らすのもおすすめです。
チャイルドシートを室内に置き、少しの時間だけ座らせて絵本を読んだり、
お気に入りのぬいぐるみと一緒に座る練習をしてみましょう。「座る=楽しい場所」という記憶を作ることができれば、
実際のドライブでも安心感が生まれやすくなります。
🌡 快適さを見直す
嫌がりの原因が、“姿勢”や“暑さ・寒さ”の場合も多いです。
ベルトの高さ・角度が合っているか、季節に合った素材のクッションかなど、
一度じっくりチェックしてみてください。
とくに赤ちゃんの成長に合わせて、チャイルドシートの設定を調整することはとても大切です。
肩ベルトの通し位置やリクライニング角度は、月齢が上がると合わなくなることがあります。
サイズが合っていないと、窮屈さや圧迫感を感じて、嫌がるきっかけになることも。また、冬は厚着による締めつけ、夏は背中の蒸れが不快のもとになりやすいです。
「少しでも気持ちいい空間」に整えることが、信頼を取り戻す第一歩。
下の子やきょうだいに引き継いで使うときも、チャイルドシートの状態や型が合っていないと、違和感から嫌がることがあります。こちらの記事(チャイルドシートきょうだい使い回しレビュー)も参考にしてみてください。
🧸 子どもに“選ばせる”
2〜3歳頃の「自分で決めたい」気持ちが強い時期には、
小さな選択肢を渡してあげるのも効果的です。
「どっちのぬいぐるみ連れてく?」
「ベルトはママと一緒にカチンする?」
“自分で選べた”という体験が、ぐずりを減らすきっかけになります。
💬 販売員として感じること
店頭でも、「嫌がるから乗せない日がある」という声を聞くことがあります。
でも、そこから戻すのは、思っている以上に大変です。だからこそ、泣いても“安全の席”を続けるほうが、結果的に親も子もラク。
少しの我慢が、大きな安心につながります。
「泣く=失敗」ではない
チャイルドシートに乗せるたびに泣かれてしまうと、
「やり方が悪いのかな」「かわいそうなことをしてるのかな」と感じてしまう人も多いと思います。
でも、泣くことは失敗ではありません。赤ちゃんは、泣くことでしか気持ちを伝えられない。
それは「嫌い」というよりも、「まだ慣れていない」「ちょっと不安」というサインです。
💭 泣いても“安全な場所”にいられた経験が大切
泣いてもチャイルドシートから降ろしてもらえなかった。
でも、車から降りるとき必ず笑顔で抱っこされた。
そんな積み重ねが、子どもにとって「チャイルドシート=安心できる場所」という記憶につながっていきます。
一方で、「泣けば降ろしてもらえる」と学んでしまうと、
そこから習慣を立て直すのは難しくなります。だからこそ、“泣いても安全な席”を続けることが、親のやさしさでもある。
🌿 泣かない日が増えていく
最初は毎回泣いていても、
“いつものこと”として淡々と続けていくうちに、泣かない日が必ず増えていきます。泣き止ませようとするより、「今日も安全に座れたね」と声をかけて、
できたことを一緒に喜ぶほうが、子どもの心に安心が残ります。
✨ 親も自分を責めないで
チャイルドシートを続けることは、子どもの命を守る行動。
泣かせたからといって、愛情が足りないわけでも、接し方が間違っているわけでもありません。泣いても安全を優先できる親は、十分やさしい。
その判断こそ、子どもを守る“本当のやさしさ”だと思います。
まとめ
チャイルドシートを嫌がらないようにするには、
まず「車に乗る=チャイルドシートに座る」を、最初から当たり前にすること。
そのうえで、泣いても焦らず、安心できる環境を整えながら続けていくこと。
泣かせたくない気持ちと、安全を守りたい気持ちは、どちらも親のやさしさです。
でも、安全は“別の次元”にある。
泣き声の一瞬よりも、守れる命のほうが、ずっと重い。
泣かないことがゴールではなく、
“安全に座れる習慣を続けられること”こそが、親の努力の証。泣いてもいい。
焦らなくていい。
そのたびに「今日もちゃんと守れた」と、自分を褒めてください。
🐰 関連記事
- 📖 チャイルドシートとジュニアシートの違い|ややこしい呼び方をスッキリ整理!
- 📖 ISOFIXでも油断禁物!取り付けミスあるあると正しい確認方法
- 📖 チャイルドシートきょうだい使い回しレビュー|安全に使える?販売員が解説